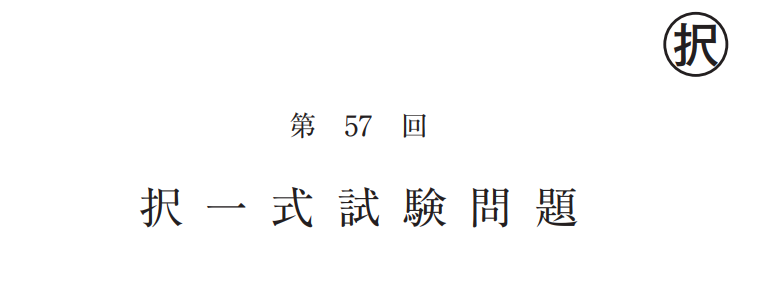
令和7年度の本試験を受験された皆様、本当にお疲れさまでした。
昨年も感じたことですが、年々択一式試験が難化しているように感じます。
この難化しているように感じる違和感は何なのかを言語化するのが中々難しいなと思っているのですが、私なりの考えをまとめみました。
昨年は健康保険法について記事にして跳ねましたので、今年も擦りにきましたよ!!と思いながら、 少しでも受験生の参考になれば幸いです。
なお、本記事は1人の社会保険労務士としての個人的見解となります。
択一式試験が難化したように感じた原因
大きく分けて、3点あると考えています。
- ①確答できる問題の減少
- ②2択まで絞ることができない
- ③応用力が問われる問題が増えた
1つずつ説明していきます。
①確答できる問題の減少
はいこれ!絶対にこれ!!1点ゲットや!!!
と確実に判断できる問題が多ければ多いほど、できた感が増していきます。
典型問題としては数字が間違っている肢などで確実に判断できた場合になります。
絶対的自信を持って1点を獲った感覚のある問題ですね。
これが今年は少なかったように感じます。
この記事を作成中にされたポストです。
あっ、金沢先生も同じ感覚だったんですね!そうなんです!!と嬉しくなったんですが、いや、このあと同じような内容を記事にしたらパクリって言われますやん!って記事作成中にちょっとへこみました。
鮮度とスピードはやはり大事だなと思いながらも、ブログの利点をいかしてじっくり具体例も交えて詳細に書いていきます。
② 2択まで絞ることができない
択一式試験の実力を測る一つの通過点として、3肢は正誤判断ができて2択まで絞れるようになるか、というものがあります。
2択まで絞って最後の決戦投票をする、というものです。
今年はそもそも2択まで絞れるような問題が少なかったように感じます。
絞れても3択までしか絞れない問題が多かったです。
確答できた問題が多ければ多いほどできた感は増します。
2択まで絞って決選投票をした問題が多ければ多いほど、手応えは減っていきます。
今年はそもそも2択まで絞るところまでたどりつくことができなかったので、まったく手応えを感じることができなかった。
というのが多くの受験生が感じたことだと思います。
なぜ絞り切れなかったのか?
絞り切れない理由は、知らない論点、見たことない問題が出るからです。
知らないから正誤判断できずに残すことになり絞れないのです。
昨年の4350円のように見たこともない、聞いたこともない数字の問題がでることがあります。
このような問題が出れば正誤判断できずに肢を消去することはできません。
そのため、残した肢で判断する必要があります。
この残った肢はだいたいが2肢くらいまでは絞れるのですが、今年はそもそも2肢まで絞り切れなかった、というのが大きな理由になります。
となると、今年は知らない論点、見たことがない問題が多かったのかというと、そういうわけではありません。
もちろん、絶対に知らないよねという問題、肢もありましたが特に多かったというわけではありません。
基本論点だけで素直に判断できない肢が増えた、というのが絞り切れなかった一番の要因となります。
聞いたことのない問われ方、知っている論点なのにいつもと違う問われ方をしているであったり、論点を複合させて読解に時間のかかる問題が増えた、ということです。
ただし、これは知らない論点、見たことない問題ではありません。
「知っているけど、わからないから知らない論点のように感じた問題」となります。
つまり、応用力が問われた問題となります。
ここを突破できるかどうかが合格点を取れるか否かの分岐点となりました。
③応用力が問われる問題が増えた
知っている論点なのに、知らないように感じる問題が多かったです。
ですが、これは知っている論点を応用させて考える必要があります。
例えば、労働基準法 問6の割増賃金に関する問題です。
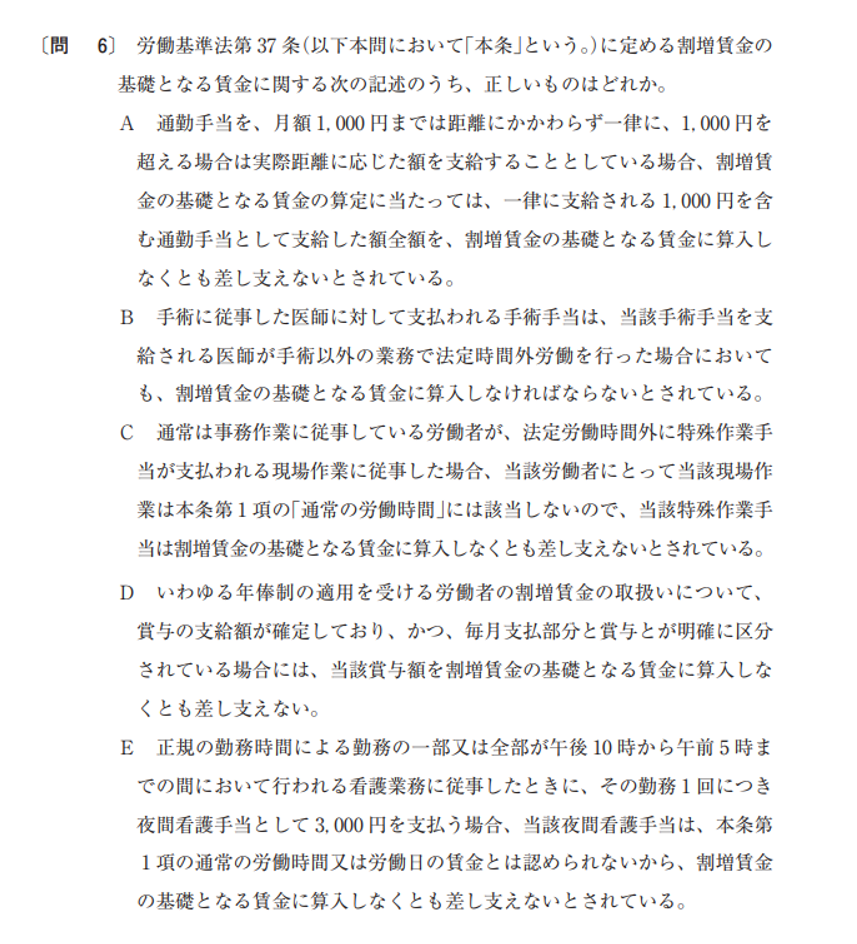
問題文を読んで割増賃金の基礎ね、はいはい、かつべしじゅうりんいちね、と思って肢を読み始めます。
A:通勤手当ね、除外!ん、1000円まで一律?1000円超えたら追加支給? なんやそれ?
B:医師の手術手当?かつべしじゅうりんいちにないやん?なんやそれ?
C:事務員の特殊勤務手当? かつべしじゅうりんいちにないやん?なんやそれ?
D:年俸制の賞与? かつべしじゅうりんいちにないやん?なんやそれ?
E:夜間看護手当? かつべしじゅうりんいちにないやん?なんやそれ?
唯一かつべしじゅうりんいちに該当している通勤手当はこねくり回されて原型をとどめず、その他はかつべしじゅうりんいちに当てはまらない。
うーん、全部なんやこれ!知らんがな!誰が知ってんねん!
と思われたかと思いますが、そうではありません。
りん(臨時の賃金)は賞与のことを指すのでDはかつべしじゅうりんいちに該当します。
素直にかつべしじゅうりんいちとは書いてくれないのです。
ただし、そう判断できたとしても「年俸制で支給額が確定して区分されている」等のこねくり回された部分のせいで確実な正誤判定はできなかったと思います。
そして、なんか不安になってこねくり回されて原型をとどめてないけど唯一該当する通勤手当の肢を選んで間違いとなってしまうんですよね。
今年、こういう問題がめっちゃ多かったです。
確かに、手術手当も特殊勤務手当も夜間看護手当も知らないかもしれませんが、知っている論点のかつべしじゅうりんいちにどう当てはめるかを応用して考えることが必要になります。
念のためですが、この問題の肢はすべてほぼ通達のままの文書となります。
解像度を上げる
応用力をつけるということは私の師、早苗先生の言葉を借りるなら解像度を上げる、ということです。
かつべしじゅうりんいちを押さえたうえで、かつべしじゅうりんいちに当てはまらない例外はあるのか、それに関する通達も読んだか等の論点の理解の深さともいえるかもしれません。
肢を見た時に、肢の論点はどこにあるのか、これを正確に判断するのが解像度を上げるということです。
試験講評LIVEで早苗先生が伝えていますので、ご覧いただければ幸いです。
注意
スタディングの仕事をしているときの私と、ブログやXの私は別人格とお考え下さい。
スタディングの仕事をしているときの私はめちゃくちゃいい人を演じています。
今後、どう対策をすればいいのか?
今年の試験を受けて、今後どうすればいいのかわからないとなった方は多いと思います。
その状況で「解像度を上げる」と抽象的なことを言われても余計に混乱させてしまったかもしれません。
今後の対策としてまずお願いしたいのは、知らない肢が多かったと思っている方は、それが本当に知らない肢だったのか、知ってる論点からわかる問題だったのかどうかの検証をしてほしい、ということです。
昨年の記事でも、知らない肢はできなくていいと書いています。
これは変わりません。
重要なことは、それが本当に知らない論点だったのか、ということです。
今年初めて問われた論点をすべて網羅し、出るかもしれない未出題論点に手を広げるのは対策ではありません。まずは、本当に知らなかったのか、知っている論点で判断することができなかったのか、というところを検証してください。
その作業の中で理解度が深まり、解像度を上げることができる作業となります。
今年の試験問題をお手元にあるテキストで調べながら、検証する作業は必ず行っていただきたいと思います。
とはいえ、今年の雇用保険法はやりすぎだと思います。
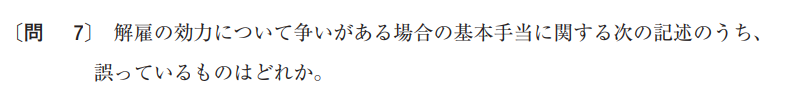
こんなんわかるわけないやろ!!
まとめ
昨年の4350円は短くいじるにはもってこいのフレーズでした。
今年で言うと、事業主夫婦の寝込みを闇討ちして自●された方や、施行令ままの表現だったパワー・シヨベルなどいじりたい部分はたくさんあったのですが、昨年のインパクトを超えれそうにないので見送り、無念な思いはここに置いておきます。
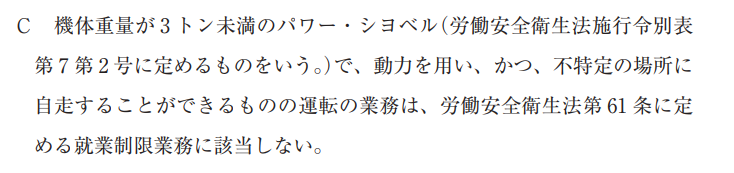
うん、やっぱシヨベルはショベルに修正してほしかったよね。
めっちゃ気になったわ。正誤判断できないことよりも気になったわ。
昨年は4350円への苛立ちから共感がたくさん生まれて笑いありの記事を書けたというドヤ感があったのですが、今年はあまりうまく記事にできなかったな、というのが正直な感想です。
感覚的な部分が大きいので、論理的な説明でなかったかもしれません。
ですが、本記事を参照いただき、本試験問題の振返りしていただければ嬉しい限りです。
今年の択一式試験への恨みが少しでも晴らされることを願っています。
それでは。

